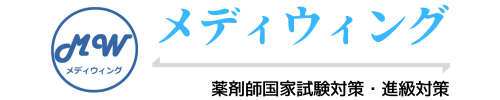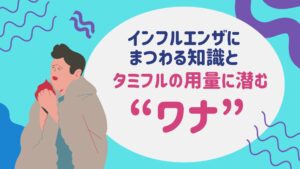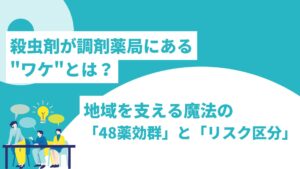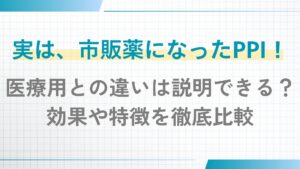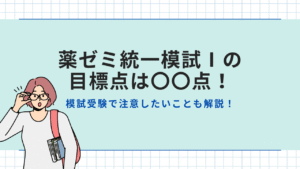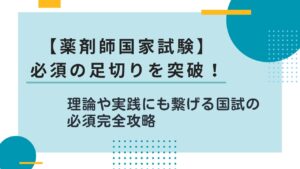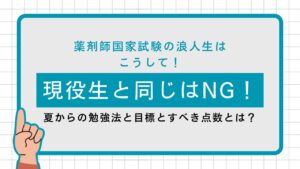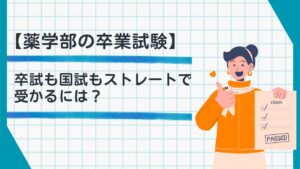【病院実習・薬局実習】商品名の覚え方!由来を知ることで広がるお薬の知識!

はじめに

実習が終わった、またはこれから控えている学生さんに立ちはだかる壁の1つに
「商品名・先発医薬品(以下、商品名)と一般名・ジェネリック医薬品(以下、一般名)が繋がらない!」
ということがあった、もしくはあるかと思います。
これらを繋げるポイントとして、
「商品名の由来を知る」
と技があります。
あなたの名前にも、きっとご両親の大切な思いが込もった素敵な由来があると思います。
お薬も同様で、市場に出るまでにたくさんのお父さん・お母さん(開発者)が
「名前を何にしよう」
と話し合いを重ねて決まります。
つまり、由来があるんです。
由来を知って、お薬の効果や知識を繋げていき、実習をより充実させたものにしましょう。
どうやって由来を知る?
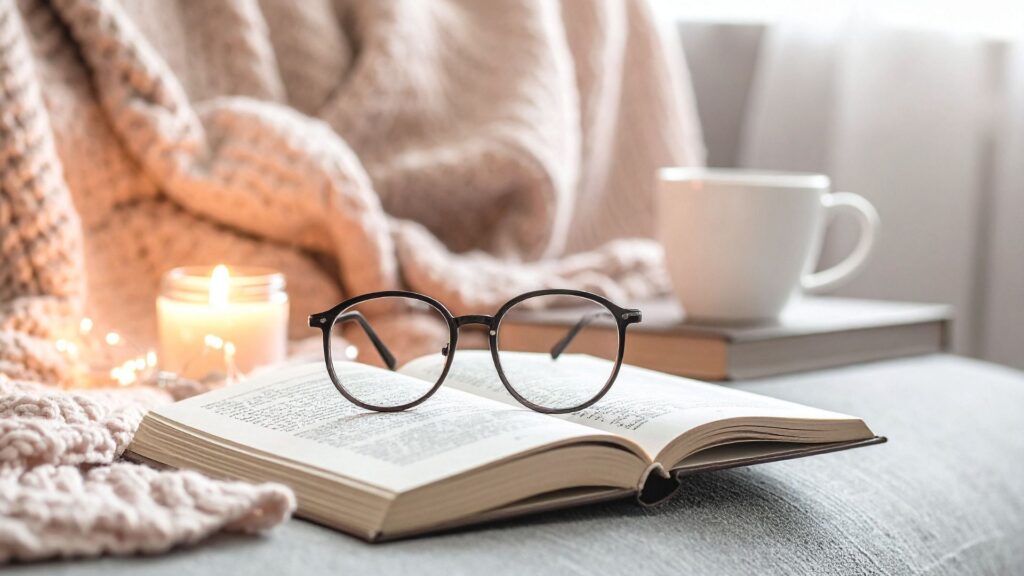
名前の由来、インタビューフォームに記載してあります。
ここでは、睡眠薬を中心にみていきましょう。
★ロゼレム(一般名:ラメルテオン)
「健やかな眠りを取り戻し、ばら色の夢を見ましょう」との願いをこめて Rose REM から名づけられた。
★マイスリー(一般名:ゾルピデム)
MY SLEEPの「MY SLEE」をとってMysleeと命名した。
★ルネスタ(一般名: エスゾピクロン)
米国で‘LUNESTA’の製品名で販売されていることから、国内の販売名を「ルネスタ」とした。
なお、Luna(=月)+Star(=星)が、米国の販売名Lunestaの由来となっている。
ただし、インタビューフォームに記載してない場合もあります。
メーカー主催の勉強会で由来を聞いたり、薬剤師仲間経由で教えてもらって知識を得ることもあります。
★アモバン(一般名:ゾピクロン)
「あぁ〜もう晩だ(から、薬を飲んで寝よう)」・・・という噂。
★ ベルソムラ(一般名:スボレキサント)
belle(=beautiful)+som(=sleep)が由来で、「美しい眠り」を指している。
ダジャレのような由来もありますね。
意外とそっちのほうが覚えやすくあります。
今回紹介した中の1つであるアモバンは、残念ながら2025年7月に在庫限りで販売を中止することが発表されました。
皆さんが薬剤師になる時期には、触れ合うことが難しいお薬かもしれませんが、
このようなお薬があったということを頭の片隅にでも置いていると、アモバンも喜ぶかと思います。
日本語じゃないの!?と勘違いするお薬も

緩下剤の1つに、商品名ヨーデルS糖衣錠(一般名:センナエキス)というお薬があります。
便秘時に使うので、
「たくさん便が出る=よう出る」
という意味!
と思いきや、
「スイスのヨーデルの爽やかな感じをイメージさせるため。また、S は superior(優れた、上質の)を意味する。」
とインタビューフォームに記載されています。
日本語は全然関係ない・・・ですが、このように偶然にも日本語として繋がるお薬もあります。
商品からその背景がわかることも

他にも面白い由来を持つお薬があります。
どのメーカーが発売してるか、商品名がヒントとなる場合があるので見てみましょう。
★タケプロン(一般名:ランソプラゾール)
タケダのプロトンポンプインヒビター
★タケキャブ(一般名:ボノプラザンフマル)
タケダのP-CAB (Potassium-Competitive Acid Blocker)
★フェントス(一般名:フェンタニル)
成分がフェンタニル+鳥栖(製造販売元の久光製薬が佐賀県鳥栖(トス)市にある。)
販売元が一発でわかりますし、効能も入っているので一石二鳥ですね。
また、日本語を交えて使っているお薬は、日本が開発したお薬の可能性がある、という知識にも繋がります。
色々と紹介してきましたが個人的に由来が好きな商品名は、めまい治療薬にも使われる「メイロン」です。
こちらは注射剤で、 私にとっての「推し由来」です!
どんな由来だと思いますか?
この記事の1番下に由来を記載しているので、予想して答え合わせしてみてください!
ヒントは「めまい」です。
薬局によっては、工夫された調剤棚もある

薬局内のスタッフ全員が、在庫しているお薬の商品名・一般名の切り替えをすぐできる・すべて覚えている、というのは経験上少ないです。
覚えていても、ふとした時に忘れることもありますし、似たような名前だと間違えることもあります。
薬局さんによっては、調剤棚の引き出しタグに
「実際に入っているお薬の商品名」にプラスして「同成分の商品名」のテプラを貼っているところもあります。
例)タケプロンが入っている引き出しに「ランソプラゾール」と記載したシールを貼る。
ランソプラゾールが入っている引き出しに「タケプロン」と記載したシールを貼る。
他にも、同成分商品同士を輪ゴムで括って引き出しに入れているところもあります。
実習生にとっては前者のような管理をしている薬局さんだと、より早くピッキングに慣れるかもしれませんね。
商品名と一般名は、覚えていた方がいい

先ほど「薬局内のスタッフ全員が、在庫している薬の商品名・一般名の切り替えをすぐできる・すべて覚えている、というのは経験上少ない」とお伝えしましたが、
1つでも多く覚えていたほうがスムーズにお仕事ができます。
「処方箋に記載されているものを、患者さんの希望通りに素早くピッキングできる」これは、最も使う場面だと思います。
イレギュラーとして、薬局から病院に電話で疑義照会したときに、内容が通じない場面があります。
ランソプラゾールの残薬があるため処方を削除してもらう内容を例に見てみましょう。
————————————-
薬局)疑義紹介お願いします。
病院)どのような内容でしょうか?
薬局)Aさんに出ているランソプラゾールが余っているので、今回削除してほしいです。
病院)ランソプラゾールという薬は処方してません。
薬局)・・・???? ランソプラゾールが処方箋に記載されているかと思うのですが・・・。
病院)商品名を教えてもらっていいですか?
薬局)タケプロンです。
病院)あぁ!タケプロンのことですね!わかりました、先生に確認するのでお待ちください。
————————————-
という場面です。
病院のレセコンでは、「タケプロン」と入力していても、処方せんに印字される時に自動で一般名で切り替えられることがあるようです。
電話口で疑義紹介したい薬があるときは、一般名と商品名の両方伝えると、病院さんにとってはありがたいことかもしれないですね。
「これ何のお薬!?先生に頼んだお薬と違うんだけど!」

こちらは、患者さんが勢いよく来局し、息つく間もなく興奮したご様子で発した言葉です。
普段服用しているお薬が商品名だったので、処方せんに記載されている一般名に驚かれていたようです。
商品名と一般名の繋がりを覚えておき、求める答えをすぐにお伝えできたら、その患者さんはひと呼吸置いてくださります。
冷静に、手こずることなく返答をできるように、1つでも多くのお薬を覚えておきましょう。
最後に

商品名の由来を調べることも、実習中にできる立派なお勉強です。
厚生労働省が発表した令和6年3月診療分のジェネリック医薬品の使用割合(全国平均)は、82.75%であり、前回発表分(令和5年9月診療分)と比べ0.89%ポイント増加しているデータがあります。
商品名を扱う機会が減っているデータがあるのも事実ですが、由来を知ることで、お薬たちがより可愛くみえることもありますし、愛着が湧くこともあります。
是非みなさんも「推し由来」のお薬を見つけて、実習をより充実させたものにしてください。
メイロン(一般名:炭酸水素ナトリウム)の由来は?

本剤の対象疾患である動揺病及びメニエール症候群が内耳の迷路(MEYLO)に関連していることと、 8.4%炭酸水素ナトリウム(NaHCO3)注射液であることに由来する。
という由来でした!
音の響きだけで「ン」を付けたわけではなく、ナトリウムの「N」をつけるなんておしゃれすぎます!!
素敵な意味が込められていたので、推し由来となりました。
予想は当たってましたか?
他に面白い由来があったら、是非教えてくださいね。