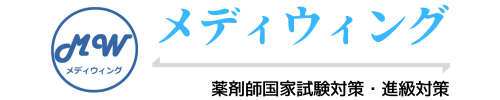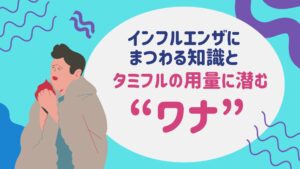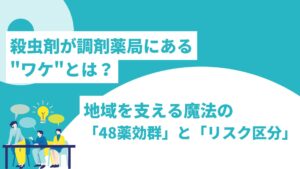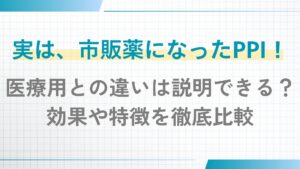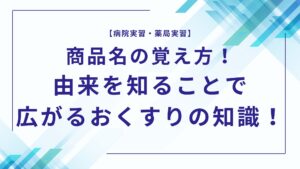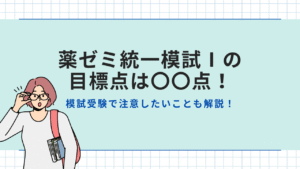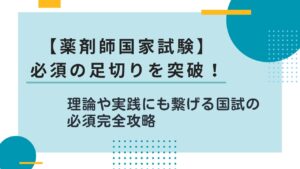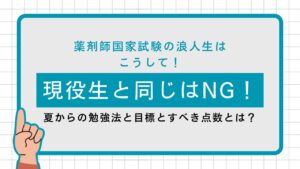ステップアップ模試って何?夏を制する3ステップ!模試後の復習完全攻略【薬剤師国家試験対策】
ステップアップ模試とは?
「ステップアップ模試」は薬学ゼミナールが夏季(例年6~7月頃)に実施する全国規模の模擬試験で、薬学部6年生を主な対象とし、春先の「スタートアップ模試」(3~4月)に続いて行われる模試になります。この模試の目的は、国家試験レベルの全範囲問題に初めて挑戦し、自分の実力や弱点を把握するとともに、長時間の試験に慣れることにあります。
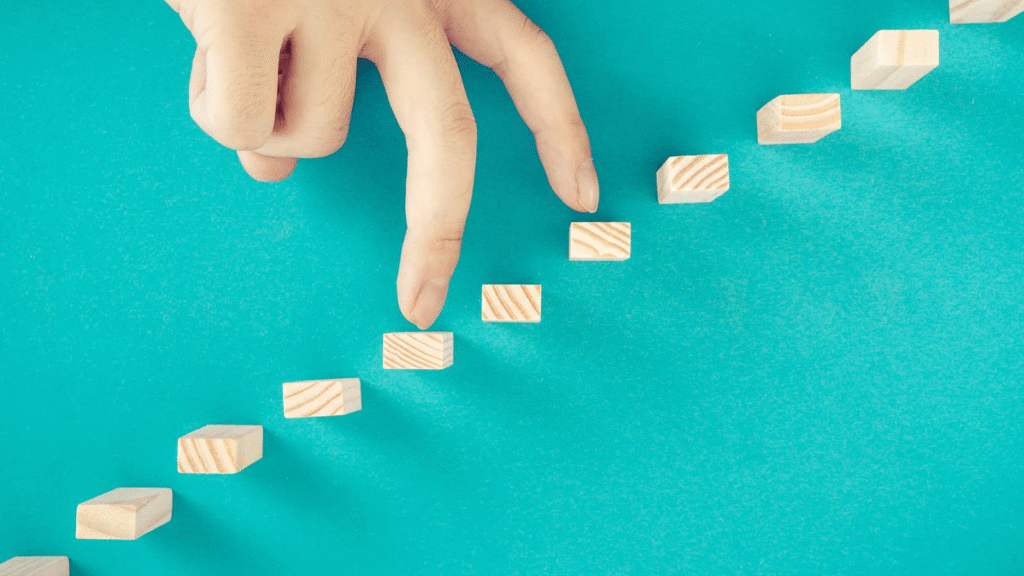
名前の通り「ステップアップ」=一段階レベルを上げる模試であり、春の基礎固めから本格的な実戦演習へ移行するステップとして位置づけられています。また、夏前のこの時期に自身の立ち位置を確認することで、今後の学習計画の修正やモチベーション向上にもつなげる狙いもあります。
出題数と出題分野
出題数は全345問で、実は薬剤師国家試験本番と同じボリュームです。内訳は国家試験の出題区分に準じており、必須問題90問+理論問題105問+実践問題150問で構成されています。
必須問題は基礎的な重要事項を問う単一選択肢問題、理論問題は薬学各分野(物理・化学・生物・衛生・薬理・病態など)の知識を問う問題、実践問題は薬物治療や調剤・法規など実務的な内容をケース形式で問う総合問題が中心です。
出題分野は薬学領域全般にわたり、国家試験と同等の科目バランスで出題されます。
難易度(本番との比較・受験者の声)
ステップアップ模試の難易度は、「スタートアップ模試」に比べて問題数・範囲が増える分難しく感じられる傾向にあります。
実際に模試の平均得点率もスタートアップ模試より低下する傾向があります。
ただし一方で、過去問が100問含まれるため、事前に過去問暗記で対策していた学生にとっては得点しやすい部分もあります。つまり、しっかり過去問演習をしていた人は実際の実力よりもやや点数が高めに出てしまいます。
受験者数が本番(約1.3万人)より少なく学力層に偏りが出やすいこともあり、この模試の結果はあくまで途中経過と捉えましょう!
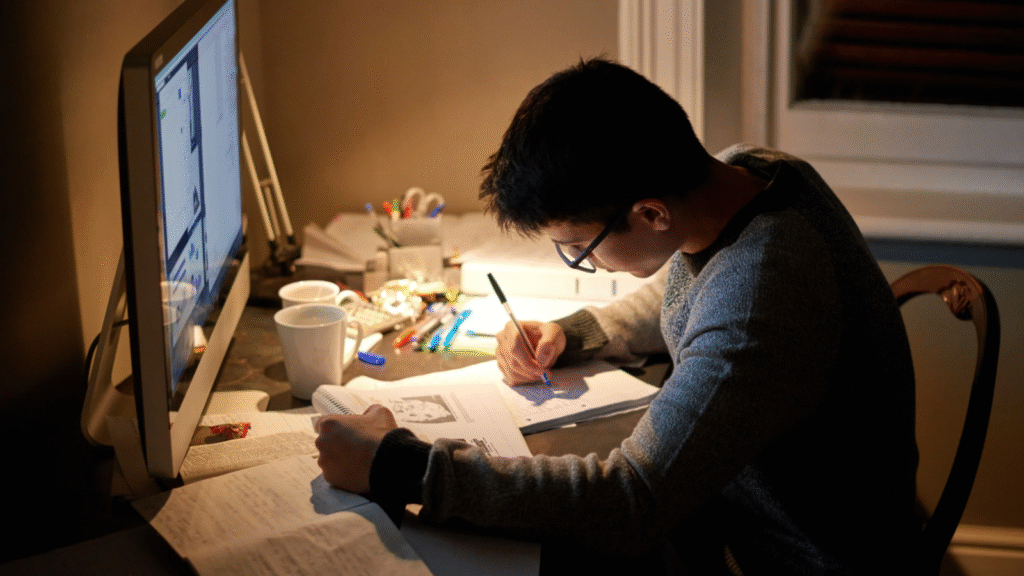
ただし、全体の40%に届かない方や過去問演習をして答えを覚えてしまい点数が伸びた人は、次の統一1に向けて何かしらの対策が必須になります。実際、ステップアップ模試から対策を始めた人と、統一模試五から対策を始めた人には大きく得点の伸びに差が出てきてしまいます。
理由としては、国家試験が相対評価であるということがあります。先輩方の声として「統一模試後はみんな努力して点数を伸ばすので、点数自体は伸びても順位は上げにくい」と言われる方もおられます。
まだ周りが本腰をいれる前の段階で、対策を入れていく必要があります。
受験者数と成績動向(平均点・得点分布)
ステップアップ模試の受験者数は全国で約5,000~6,000人規模です(例:2022年は5,767人が受験)。
これは国家試験受験者全体(毎年約13,000人)のおよそ半数程度で、秋以降の「全国統一模試」(各回1万人超)よりは規模が小さめです。
平均点は毎年異なりますが、概ね総合得点で150~170点前後(345点満点中)になる傾向があります。
たとえば2022年のステップアップ模試では、平均点は166.6点でした。得点分布を見ると、過去問対策が功を奏した一部上位層は高得点を取るものの、6月時点では受験生全体の半数以上が5割未満の得点率に留まっています。
2022年のデータでは筆者は229点を獲得して全体の上位7.8%(Aブロック)に入りましたが、平均付近は約167点、最頻得点帯も150点前後に集中していました。
成績表では成績上位者にはA~Eのブロック判定も付与され、自分のおおよその順位層がわかるようになっています(Aブロック=上位約10%、Bブロック=上位30%程度、等)。このような全体分布と比較することで、自身の相対的な位置や科目別の強み・弱みを把握できるようになっています。
上位60%に入れなかった人や答えを覚えてしまっていた人が模試後にやるべきこと
模試実施後に詳細な成績表(個人カルテ)や解答解説集が渡されると思いますのでまずは自分の弱点を分析しましょう。
まずは模擬試験を見直す

各教科ごとに網掛け問題(正答率が高い問題であるにも関わらず自分が落としてしまった問題)が成績表に記載されていると思いますので、その問題をまずは復習しましょう!模擬試験を受けっぱなしにしてしまうとどうしても点数は上がりにくくなってしまいます。
国家試験では正答率が60%以上の問題を獲得できていれば合格すると言われていますので、周りの方ができている問題には必ず取り組むようにしてください。
今の勉強法を見直す
模擬試験のカルテでは、「どの科目を重点的に復習すべきか」「自分だけ落としている基礎問題はどれか」が一目で分かるよう工夫されています。
得点が取れなかったのには必ず理由があります、理由としては以下のことが該当します。
・未習得・理解不足の範囲が多い
└学習が追いついておらず基礎知識や重要事項の理解が不十分だと正答率が下がります。
・学習計画が曖昧/未策定
└何をいつまでに仕上げるかの目標が明確でないと、優先順位がつけられず進捗も管理しにくいです
・苦手分野の偏りを見直す
└特に苦手な科目を後回しにし過ぎると総合点が落ち込みがちです。科目ごとのバランスも大切です。
対処法をいくつか紹介します!
① 未習得・理解不足の範囲が多い
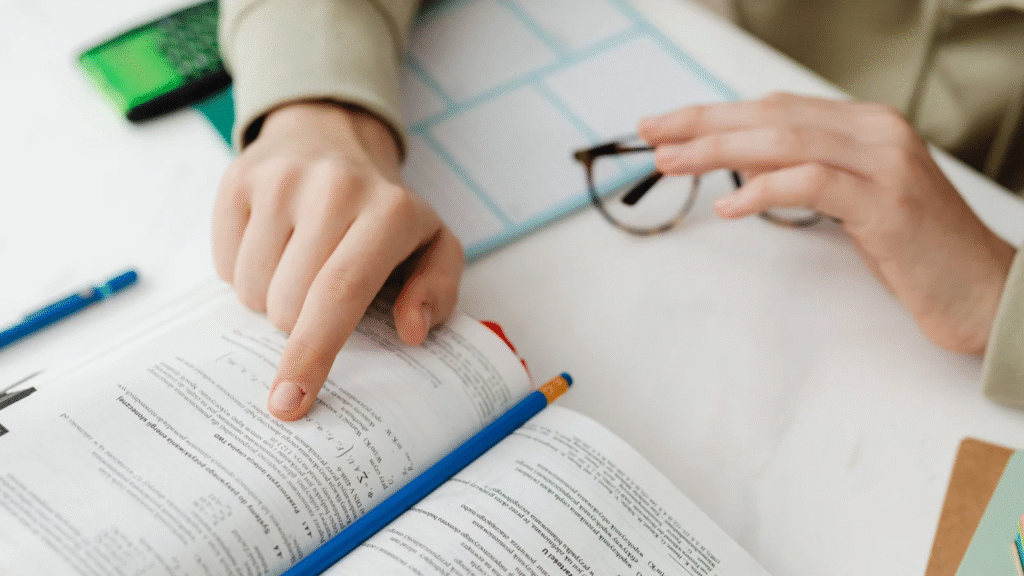
▷ 特徴
- 必須問題の落としが目立つ
- 解説を読んでも「なんとなく」で流してしまう
- 「暗記はしたけど、実戦で使えず点数が伸びない」状態になっている。
▷ 対処法
| ステップ | 具体策 | 目安 |
|---|---|---|
| Check | 模試カルテの正答率60%以上で落とした問題に赤印 | 模試翌日まで |
| Understand | 青本・講義動画で“原理→公式→例題”の順に再学習 | 1問=15分 |
| Practice | 同テーマ過去問を2年分連続で解き、自力再現 | 覚えた直後24h以内 |
“1テーマ90分完結”ルール
90分以上かけると集中力が切れ、深い理解に結びつきません。タイマーで区切って回転率を上げましょう
② 学習計画が曖昧/未策定

▷ 特徴
- 今日は化学、明日は病態…と気分で科目が変わってしまう
- 「今週200問解く」が終わらず、翌週にタスクが雪だるま式になってしまう…
▷ 対処法
- 目標スコアを具体化
- 例:統一模試Ⅰで+30点(必須+10/理論+10/実践+10)
- 例:統一模試Ⅰで+30点(必須+10/理論+10/実践+10)
- “逆算ガントチャート”を作る
- 8週後に達成するには1週あたり何をすべきかを長期目標から短期目標に落とし込み、具体的な1日毎のタスクにする
- GoogleスプレッドシートやNotionで共有→進捗の可視化しましょう
- 週末レビュー&翌週修正
- “終わらなかったタスク”を翌週にそのまま移すのは禁止。必ず週末までに終わらせてしまいましょう!
- 未消化タスクは“原因メモ”を添えてボリュームを半減→再割り当てをしましょう
黄金比:インプット3割・アウトプット7割
ステップアップ模試以降はアウトプット比率を急上げしよう!
③ 苦手分野の偏りを見直す

▷ 特徴
- 「物理は苦手だから後回し」が習慣化してしまっている…
- 模試成績表のレーダーチャートが“歪(いびつ)”になっている
▷ 対処法
- 1日1弱点ルール
- 毎日最初の60分は“最も嫌いな科目”から着手。脳が元気なうちに処理しておきましょう
- ペア学習でアウトプット
- 苦手科目は「友人へ“5分講義”」すると定着率が上がりますよ!
- 科目横断リンク集を作成
- 例:βラクタム系は「化学構造(化学)→作用機序(薬理)→耐性菌(衛生)」といった形で一本線でつないでみましょう
- “合格点カット”戦略
- 苦手科目を完璧にするのではなく、「合格ボーダー(60%)」到達ラインを先に設定。残りは得意科目でカバーしましょう
コラム:歪みは早期修正が最小コスト
苦手科目が“沼化”すると直前期に膨大な時間を奪われます。夏から少しずつ取り組んでおくと後がラクです
勉強法のまとめ
- 模試分析 → 90分集中学習 → 即アウトプット → 週末レビュー
- 計画表で進捗を見える化しましょう
- 1日1弱点+ペア講義で苦手を潰す
このループを回し続ければ、統一模試Ⅰ(9月)までに+30〜50点は狙えます。時間は有限。今日から“仕組み”で学習を最適化しましょう
無料学習相談実施中!
「自分の弱点診断がうまくできない」「計画立ての作り方がわからない」などお悩みがあれば、LINE公式で無料相談を受付中😊
- カルテ添削&学習計画提案を個別でお伝えします!
- 国試だけでなく、卒業試験も合わせて乗り切る個別プランをお伝えします!